|
|
|
|
|
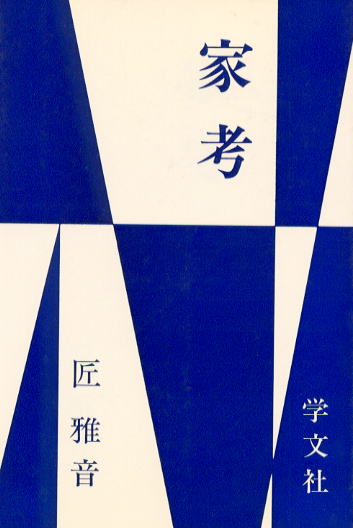 |
|
1986年出版 |
はじめに
自分の気に入った家作りは、とても難しいものです。
あなたのライフスタイル、もしくは生活の仕方、これこそがあなたの家を作らせる原動力です。
しかし、ライフスタイルと言うだけでは具体的ではないし、よくわからないでしょう。
自分の考えは他人の考えと比較してはじめて、正確に自覚できるものです。
ですから、ただ、自分のスタイルを考えることだといっても、とりとめもなく感じることでしょう。
そこで、匠研究室の考えたスタイルを述べてみましょう。
これを叩き台として、あなたの家作りにいくらかでも役にたてば幸いです。
ある時は、建築のカとは恐しいものだと思います。
その建物がたったために、街の景観が一変したりします。
また、部屋の内装を変えると、まったく別の部屋であるかのような錯覚にさえ、おちいらせてくれます。
建築が人間の感情的な面に、直接働きかけるカをもっていることは、他の芸術と似ています。
しかし、建築には、絵画や音楽と異なり、使用されるという特徴があります。
とくに住宅の場合は、そのなかに人が住むという属性を、切りはなしては考えられません。
住めない住宅でも、建築することが不可能な住宅でも、建築理論上は一向にかまわないのですが、多くの場合、それでは建築主をみつけだすことは無理でしょう。
また、あなたはそんな家を望んではいないでしょう。
建築の歴史のなかでも、さまざまなことがいわれてきました。
立派な建築理論を身につけた設計者によって、たてられた住宅もたくさんありました。
しかし、100パーセントの住宅が、住み手や建築主、つまり建築費をだしてくれる誰かをもっていました。
新しい住宅の住み手は設計者ではありませんから、その家に設計者が住むわけにはいきません。
新しい家は住み手のために作るのですから、設計者が住んでも何の意味もありません。
住み手と設計者の考え方がまったく違った場合は、もう悲劇をとおりこして、喜劇ですらあります。
そうした悲喜劇に立ち至らないために、住み手と設計者とのあいだに、生活に対しての共通の考え方のようなものがないかと考える次第です。
それが共有できれば、両者の意思の疎通は、ずっと簡単になるはずです。
設計者には悪いくせがあります。
それは外国語を、カタカナのまま持ち込んでしまうことです。
生活の様式や家自体は日本そのものであるのに、外来語を未消化のまま持ち込んで、その言葉によって何かを作ろうとしてしまうことは、じつに始末が悪い話です。
リビングルームやファミリールームとはいったい何なのでしょう。アメニティとは?
外来語によってしか、表現される現実しか日本にはないのでしょうか。
私たち日本人の生活を考え、表現するのに外来語を使用しなければならないとしたら、日本語は何と貧しい言語なのでしょう。
いや、本当は日本語が貧しいのではなく、あやし気なカタカナ語を使用することが、何かかっこうよいかのように錯覚しているだけだと思います。
そして、カタカナ語の多用は、売らんかなの商業主義が、何とか目先を変えて売るための、麻薬のような幻覚作用ではないか、と匠研究室では疑っています。
リビングルームやファミリールームと、その部屋が名付けられていたとしても、私たちがそのなかで生活します。
私たちの生活は、家のなかでも靴をはいたままではありません。
かけがえのないあなただけの家作りは、あなたの生活をもっともたいせつなものと考えます。
いったい家とは何なのかということを考えておいても、けっして無駄ではないと思います。
誰もが住んでいる家。家という言葉はとても日常的な言葉です。
身に付いた自分たちの言葉で、家を丸ごと考えてみましょう。
|