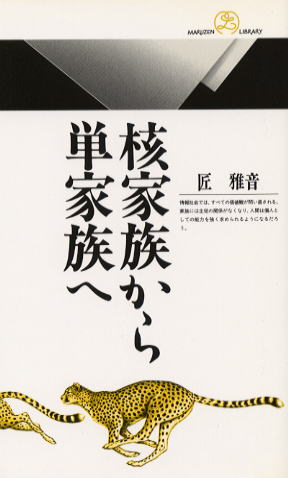|
||||
| 「単家族の誕生」は「核家族から単家族へ」の第1部第1章と第2章を抜粋したものです。 <はじめに−等価なる男女>が、愛知大学の入学試験の国語で出題された。 | ||||
|
|
||||
|
||||
|
はじめに−等価なる男女 家族の小型化とかシングルズの増加という家族の多様化が、脚光を浴びるようになって随分と時間がたつ。 その時代の産業社会の変化と、緊密に連動している。 今世界中で、産業社会は劇的に変化しており、新たな時代を予測させる現象が次々に起きている。 家族も社会的な存在だとすれば、家族構造の変化も産業構造の変化を反映したものだ、とみなすほうが自然である。 わが国でも産業社会は激変しているので、わが国の家族も先進諸国と同じように次なる形へと移行する。 情報社会へ突入する今後の産業構造は、ますます個人化した生活を求めてくる。 それゆえ、家族の構成員数は、減少することがあっても増加することはない。 それを知ったとき、家族に関する諸現象を否定的に見ることはできず、変化は時代が必然的に生み出すものだと認めざるを得なくなった。 工業化の進展とともに大家族が核家族になったように、現在進行している家族の変化も、何らかの社会的な背景のもとに、規則性を持って展開している。 西洋諸国で始まった近代化=工業化は、19世紀にわが国に飛来し、今や東および東南アジアへと広がっている。 その軌跡には、土地(農業)から物(工業)へ、物(工業)から知識(情報)へ、という共通した流れがある。 この流れが産業構造を決定づけ、それに続く社会現象を引き起こしている。 すべての先進工業国は今、競って情報社会をめざしている。 これを不可避だと確認する時、家族だけが現状のまま留まるはずはない。 とすれば、歴史の流れにそって家族構造の変化に規則性を見いだし、新たな時代に対処すべきである。 ただいたずらに、古き良き家族生活を懐かしんでも、回復されることはないのだから。 新たな現象が発生する時、それを表す言葉はない。 ここでも新しい家族形態を表す言葉はなかった。 そこで、「単家族」という言葉を作らざるを得なかった。 現代の家族形態の変化を、核家族から単家族へととらえることによって、現在発生している社会現象が整然と理解できた。 いま本書を書き上げて、眼前を進行中の社会変化を、観念がやっと追認できたと感じる。 と同時に、世界ははるか彼方を走っていると、改めて知るのである。 肉体が支えてきた文明が第一位の座からおり、その有効性を失いつつある。 それにかわって、頭脳労働が上位の価値となり始めた。 肉体労働の象徴である農耕社会や工業社会の価値観が、まったく有効性を失ってしまうかも知れない状態に、今、私たちは立ち至っている。 肉体労働から頭脳労働への転換が、肉体的な非力さを無化した。 肉体的な非力は、もはや劣性ではない。 そしてそれが、女性の台頭を促した。20世紀最大の歴史的事件は、女性の解放であることは間違いない。 しかしことは、それにとどまらない。 女性の台頭は、男性であることや女性であることを貫いて、人間の認識や存在そのものを問うている。 これは男性とか女性とかの問題ではなく、人類そのものの問題なのである。 歴史の流れを、筆者は大きく次の三つに区切って、考えている。 それは、1.農耕社会 2.工業社会 3.情報社会である。 そして、三つのそれぞれの時代には、次の関係が成立している。
農耕社会とは、人類が初めて地上に降り立ってから、狩猟・採集の生活をへて、農耕・牧畜など土地を生活資源としていた長い長い時代をさす。 一人の子供が結婚すると、その子供夫婦が親夫婦と同居し、そのほかの子供たちは独立して外へでることが多い直系家族は、もちろんのこと大家族と見なしているし、一夫多妻・一妻多夫など一対の男女以外にも成人が同居する家族形態を総称している。 それゆえ本書で使う大家族は、血縁がない奉公人や作男などを疑似家族員として、抱え込むことができるのである。 工業社会とは、産業革命によって工場や会社という労働の場をつくり、土地以外に労働の対象を作りだした時代をさす。 工業社会になって、土地から物へと労働対象が移ったのである。 わが国では、明治維新から始まった西洋文明の移入期から、コンピューターが登場するまでをさしている。 西欧諸国にあっても、農耕時代の最後と工業時代の初めは重なっており、産業革命によって社会が瞬時に変化したわけではない。 西洋諸国もまた、ゆっくりと相当に時間をかけて変化してきたことは当然なので、どの瞬間をもって工業社会の成立と見るか難しい。 だからわが国でも、戦前はやはり移行期としておく。 工業社会になったからといって、農業がまったくなくなってしまうわけではない。 新たな労働の場が発生し、より生産性の高い経済活動の分野が、工業に移動するだけなのである。 ちなみに、農耕社会→工業社会→情報社会にかんするこの式は、わが国のみに妥当するものではなく、地球上のどの地域にも適用できるものとして考えている。 情報社会とは、農業・工業社会がともに物の生産をめざしたのに対して、無形の知識や考え方といった情報が有償で取り引きされる社会をさす。 ここで人間は、土地ばかりではなく物の属性からも離れ、より自由に幅広く経済活動ができるようになった。 それゆえ情報社会とは、コンピューターの登場以降をさし、現在の社会がまさにそうである。 しかし、農耕社会から工業社会への移行に、約5〜600年かかったことを考えると、現在は情報社会のほんの入り口にたったところだと、考えたほうが適切である。 工業社会に農業が残存するように、情報社会になっても、工業や農業がなくなるわけではない。 人間はものを食べないと生きていけず、食べ物をつくるのは農業だから、どんな社会になっても農業が絶無になることはあり得ない。 工業にしても同様で、情報社会になったからといって、工業がなくなることはあり得ない。 情報社会を支えているのは、農業であり工業である。 つまり、時代の価値が情報に移行しただけであって、情報社会には情報しかないわけではない。 肉体的に屈強なほうが、より高い生産性=経済力があったのである。 経済的に必要度の高い者が、社会的にも上位に置かれるのは自然の成りゆきである。 それゆえこの時代までを、男性支配の時代だと筆者は考えている。 本文のなかで、農耕社会は男女平等だったと誤解させやすい記述があるかも知れないが、今日まで男女がほんとうに平等だった社会は存在しない。 いつでも地球上のどこでも、男性が支配する社会だった。 農耕社会や工業社会にも、先進的な女性による女性の権利拡張をはかる運動はあったが、そこでは肉体労働が生産の根底を支えたので、女性の台頭は生活の次元まで降りることができず、一般性をもたなかった。 コンピューターの登場により、労働に肉体的な腕力が不要になり、頭脳労働の比重があがってきた。 情報社会では、肉体的に強い腕力は不要である。 そこで労働の場において、女性の非力さが不利な要因ではなくなってきた。 肉体的な劣者でも頭脳さえ優秀であれば、屈強な肉体をもった者以上の経済活動ができるのである。 つまり、労働における男女差は無化されたのである。 そのため情報社会に入ると、男性支配の時代は終わり、男女が等価にして平等になりつつある。 農耕社会そして工業社会まで、信頼できた価値観の体系は、ほころび始めた。 情報社会では、既存の価値観が問い直される。 情報社会において家族が個化し、すべての人間は個人としての能力が問われざるを得なくなる。 核家族が支配的だった工業社会から、情報社会では、個人を単位とする家族=単家族へと移行していく。 時代の変遷が不可避であると知るとき、新たな認識の基盤がどうしても必要になる。 本書における筆者の問題関心は、そうした社会像の描写と、農耕・工業・情報という三つの社会が、同時に存在することから発生する問題の検討である。 |
||||
|
|