| 目 次 |
1章.同性愛についての予備知識
― 同性愛には二種類ある
|
2章.ゲイの認知
― ゲイのことを知るには
|
3章.ホモとゲイ
― ゲイは新しく生まれた
|
4章.性的少数者
― 世の中にはさまざまな人が生きている |
5章.ゲイの破壊力
― 遅れてきた自由を求める人々
|
6章.性的人間関係
― いまは混沌としているけれど
|
7章.開かれた世界へ
― 全員が普通に生きていくために |
あとがき |
たくみアマゾンで『ゲイの誕生』をお買い求め下さい
|
まえがき
今では男性間の性愛行為を同性愛といって、女性相手の異性愛と区別する。しかし、かつては成人男性にとっての性愛行為は、相手が女性でも青少年でも同じ意味だった。青少年相手の場合だけ、あえて同性愛と呼ぶ必要性はなかった。そのため同性愛という言葉もなかった。
1890年になって、「ホモセクシャル=同性愛」という言葉がイギリスで生まれた。ここで女性相手の性愛行為と、青少年相手の性愛行為が区別されて、別のものと見なされるようになった。同性愛という言葉が生まれたので、その反射的な効果として、男女間の性愛行為を異性愛と呼ぶようになったのである。
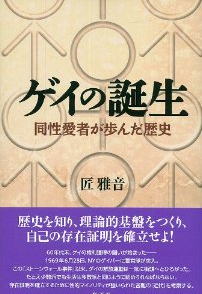 |
| 彩流社刊 ¥2500−(税別) |
1970年頃になると、西洋諸国の同性愛者が「ホモセクシャル=ホモ」と呼ばれるのを嫌って、ゲイと名乗って登場してきた。同性愛がホモからゲイに替わってしまったのだ。
若い男性を相手にセックスを行っていた成人男性が、いつの間にか成人男性を相手にして性愛行為を行うようになった。ここには性愛行為の大きな質の転換があった。この転換こそ本書が注目するポイントであり、本書が書かれた理由である。
同性愛者が生まれる原因は、胎児期におけるホルモンの影響や脳構造・遺伝などによるもので、同性愛者と異性愛者とは脳などが生理的に異なっている、という説がある。誤解されないように書いておくが、本書は同性を指向する生物学的な原因を論じるものではない。人間の生物学的な構造は古今東西で変わらないはずだから、生物学的な原因をいくら考えても、同性愛者への対応が時代や社会によって、これほど変わったことは説明が付かないのである。
ホモが消えていってゲイが生まれた。ゲイの誕生には、近代が生んだ〈自由と平等〉という、非常に重要な歴史がからんでいる。近代を考えることは、決してゲイだけの問題でもないし、性愛だけの問題ではない。少しだけ結論めいたことを言うと、ゲイの誕生とは性やセックスの問題ではなく、年長者が偉いという年齢に関する秩序とその崩壊の問題だった。
近代社会が年齢秩序の解体を要求しており、近代社会の要求にしたがった年齢秩序の崩壊が、変声期前後の青少年との性行為を許さなくなった。しかし、人間の性指向は異性とはかぎらないから、同性を指向するゲイが市民権を得てきたのである。本書はゲイの誕生を手がかりにして、近代における年齢秩序の崩壊と〈近代〉の特質を考えるものである。
|
| たくみアマゾンで『ゲイの誕生』をお買い求め下さい |